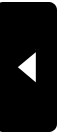2006年10月05日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(十)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(十)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐陀神能:スサノヲ命とヤマタノオロチ(2)
スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)は高天原を追放され、出雲国の肥の河上の鳥髪(船通山、一一四三メートル、大砂鉄地帯)という地に降ったと『古事記』は記している。ただ、『日本書紀』一書には、安芸の可愛(え)の河上に降ったとしたり、新羅のソシモリ(曾尸茂利)に降り、そこから船で日本の紀伊に渡るとし、また別の一書では、クマナリ(熊成)峯から根の国に渡ったとする異説を収録している。
また、『日本書紀』一書は、スサノヲ命は、長雨の降る中を蓑笠姿で彷徨い歩いたが、どこの家も留めてくれるところがなく、スサノヲ命の辛苦難渋の流浪の様子を描いている(『備後国風土記』逸文では、蘇民将来の説話として登場する。沖縄にも類似の説話がある)。
出雲の肥の河上の鳥髪に降ったスサノヲ命は、斐伊川を流れる箸をみて、上流に人がいると知り尋ねてみると、そこには国つ神・大山津見神の子でアシナズチ(足名椎・脚摩乳)、テナズチ(手名椎・手摩乳)の老いた夫婦とその娘のクシナダヒメ命(櫛名田比売・奇稲田姫命)が嘆き悲しんでいた。
そこで、スサノヲ命はヤマタノオロチ(八俣大蛇=八岐大蛇=八俣遠呂智)の生贄にされようとしていたクシナダヒメ命を助けようとする。スサノヲ命はヤマタノオロチを酒に酔わせ、眠らせておいて十拳剣で斬り殺し、肥の川は血に変わったという。
大蛇の尾を切り裂いたところ、霊剣・草薙剣(草那芸の大刀・都牟刈の大刀)が出てきたので、姉神であるアマテラス(天照大御神)に献上し、これが後の三種の神器の一つになったという。
スサノオ命は、クシナダヒメ命と結婚をして、出雲の須我(須賀)に宮殿を造って住む。このとき、「八雲たつ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を」という有名な歌を作ったという。また、この二人の間にもうけた子孫が大国主命であるとしている。
このように、『古事記』に描かれたヤマタノオロチ(八俣大蛇=八岐大蛇=八俣遠呂智)は、凄まじい形容で描かれる(『古事記』は「是の高志の八俣のをろち年毎に来て喫へり。今、其の来べき時なるが故泣く。」・・・「彼の目は赤かがちの如くして、身一つに八頭・八尾有り。亦其の身に蘿及檜・椙生ひ、其の長谿八谷・峡八尾に度りて、其の腹を見れば悉に常に血爛れたり」と記す)。これは一体何を象徴しているのであろうか。
この解釈については、斐伊川が鉄穴(かんな)流しによって水が赤く濁ったとする説、斐伊川の姿(蛇体の水の精霊)を表しているとする説(竜神に人柱として生贄を捧げていたが、治水開拓にすぐれた英雄神が河川を治めた)、出雲での蛇祭を表しているとする説、大和政権からみた出雲のイメージとする説、高志(北陸地方)人の首長であるとする説、中国山脈の鉄山と鍛冶部(かぬちべ=タタラと呼ばれる漂泊的採鉱冶金鍛冶集団)であるとする説、あるいは、シベリアのオロチ族であるとする説など、じつに様々な説がある。
他にも、もともとは「怪物と人身御供」の説話ではなく、蛇体の水神と稲田の女神との神婚説話に、新たに人間的英雄神説話「ペルセウス・アンドロメダ型説話」が包摂したとする説もある。
スサノヲ(スサノオ)
2006年10月05日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(九)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(九)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐陀神能:スサノヲ命とヤマタノオロチ(1)
日本の代表的な神事芸能「神楽(かぐら)」として「佐陀神能(さだしんのう)」(島根県鹿島町の佐太神社に江戸初期から伝わるという国の重要無形民俗文化財)(※注1)と、そこから派生し、よりエンターテイメント性豊かになった広島県高田郡周辺に伝わる「芸北神楽(げいほくかぐら)」(※注2)がある。
囃子や謡などに能の形式を取り入れた「佐陀神能」は、スサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚尊)のヤマタノオロチ(八俣大蛇=八岐大蛇=八俣遠呂智)退治に題材をとった「八重垣(やえがき)」のほか、「大社(おおやしろ)」「大和武(やまとたけ)」などを演ずる。
また「芸北神楽)」は、巨大な面、赤や緑の極彩色の衣装など、スペクタクルな演出が特徴だ。佐陀神能の「八重垣」と同じくヤマタノオロチ退治を描いた「八岐大蛇(やまたのおろち)」では、スサノヲ命とヤマタノオロチの迫力たっぷりの対決が圧巻である(口から火を噴き、暴れ回る長さ十メートルもの巨大な大蛇に、真っ向からスサノヲ命が剣で立ち向かう)。
神楽は、神を招き、その魂を鎮めるのを目的とした神事芸能である。「佐陀神能」と「芸北神楽」は、神話の世界を題材に演劇的な「神能」を演じるところに特徴のある出雲流神楽の流れを汲むものだ。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)「佐陀神能」は、島根県鹿島町・佐太神社の氏子を中心に伝承されてきた。江戸初期には成立していたという。鈴・剣・茣蓙(ござ)などを手にもって舞う採物舞「七座」「式三番」「神能」の三部構成で、囃子・謡・所作などに能の形式を取り入れている。
(※注2)「芸北神楽」は、そこから派生し、変化していった神楽で、広島県高田郡周辺に伝わっている。巨体な面、鮮やかな色彩の装束、口から火を噴く仕掛け、そして長さ十メートルにもなる大蛇など、スペクタクルに溢れており、庶民に親しまれる演出がなされている。
スサノヲ(スサノオ)
2006年10月03日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(八)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(八)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、お忌み祭(神在祭)(3)
佐太神社(※注1)では、十一月二十日(神迎え)、南北の出入り口のみを残して、本殿付近は注連縄が張り巡らされる。夜、宮司以下はこの南口より注連縄内に入り、各本殿の前で拝礼を行う(佐太独特の礼拝方法である「四方拝」を行う)。その後、直会殿の秘儀で神々を迎え、神籬(ひもろぎ)は中殿前に安置される。その後、二つの入口は青木で閉ざされ、これ以後、神職といえども注連縄内には入ることができない。
十一月二十五日(からさで=神等去出)(※注2)、白装束姿の神職は神籬(ひもろぎ)を奉持して、オーという警謐(けいひつ)の声が暗い山々にこだまする中を、神名火山に続く尾根の途中にある神目山に登り、秘祭を行う(※注3)。ここには日本海に通じるとされる池と呼ばれる小さな窪みがあり、ここに神籬(ひもろぎ)を載せた船を置くことで、神々は佐太神社を去っていくとされている。
十一月三十日(止神送り=しわがみおくり)は、二十五日の神送りと同様な行事が行われる。これは帰り残った神を送る祭礼だ(佐太神社の神在祭は他社と異なり春と秋の二回行われる)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)佐太神社のお忌み祭では、神々を二十日に神迎えして、境内に忌串を廻らして人々を近づけないようにする。二十五日の神送りの夜には、亥の刻(午後十時)に斎主は神籬を捧げ、大勢の人々がこれに従い、神目山(もと神名火山)の上まで神送りする。
神在月になると、佐陀の浦(鹿島町古浦海岸)には竜蛇が出現し、これが佐太神社に奉納されるようになった。竜蛇とは南方産のセグロウミヘビで、お忌み祭(神在祭)の頃の季節風(お忌み荒れ=晩秋、日本海に北西の風が強くなる頃、出雲の海は急に暗くなり海面は荒れて泡立つ)によって浜に打ち上げられたものだ。
この竜蛇信仰は、海の彼方から寄り来るという古代信仰(マレビト信仰、海の果ての常世国から豊饒をもたらす神、対馬海流がもたらす南方文化への憧れと信仰)を伝えるものである。
(※注2)神在祭(お忌み祭)の最後の神事で神々を送る「神等去出(からさで)さん」の日は、特に厳重に身を慎む。迎えた神々は鹿島町の佐太神社、松江市の神魂(かもす)神社などこの地方の七社にも廻ったあと、お立ちになるが、佐太神社では「水夫(かこ)」と唱えつつ神目山(かんのめやま)頂上から送る。
斐川町の万九千(まんくせん)神社では、十一月二十六日の夕方、梅の小枝で神社の戸を叩きつつ見送るが、かつては出雲の神名火山(現在の仏経山)で焚く火の中をお立ちになったという。このように海(あま)から迎え、山=天(あま)から送り返すところに、ものごとを循環してとらえる日本人の深層意識が読み取れる(お盆にも同じような習俗が残されている)。こうして人々は身を慎み、清らかな心で神々に接した後、もの忌みから解放され、晴れ晴れとした活力を感じるようになるのだ。
出雲の信仰は、縄文時代の精霊信仰を継承しつつ、弥生時代の祖霊信仰を受け入れ(このときの信仰が日本人の神信仰の基本型を形作っているようだ)、今日まで生き続けて来たことになる(北九州の勢力が縄文文化との縁を断ち切ったうえで、大陸・朝鮮半島の新しい文化を取り入れたのに対して、出雲の人々は縄文文化を継承しつつ、新しい高度な文化を取り入れた人々のようだ)。
このように、出雲から日本人の信仰の基層を見て取ることが出来そうである。小泉八雲は言う。出雲は日本の「民族の揺籃(ゆりかご)」であると。「出雲はわけても神々の国である」と。
(※注3)秘祭は二段あり、前段は頂上からはるかに見える日本海に神々を送る神事で、後段は五穀豊穣と子孫繁栄を祈願する祭りの原型らしいのだが、弥生の祭りの名残とする説もある。それと、銅鐸と銅剣が出土した志谷奥遺跡はこの山の麓である。あの青銅器はこの祭りと関係があるのかもしれない。
スサノヲ(スサノオ)
2006年10月02日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(七)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(七)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、お忌み祭(神在祭)(2)
現在では佐太神社の神在祭(お忌み祭・お忌みさん)は、新穀を神々に捧げるという新嘗祭(にいなめさい)と同義のものとして行われている(これはこの神名火山に新穀を捧げる神名火山祭に発祥しているからと考えられている)。しかし近世においては、当時の祭神・イザナミ命(伊邪那美命・伊弉冉尊)(※注1)(※注2)が旧暦十月に出雲で崩御し、神名火山の山塊にある足日山(当時はこの山が神名火山と考えられていたようだ)に埋葬されたと考えられていた。
イザナミ命は神々の母として考えられていたので、当時の神在祭は、神々が母神に対する孝行のために、その崩御した旧暦十月、埋葬された近くの佐太神社に集まるのだとされていたのである。その故か、神無月の語源について、母神の無い月と考える向きもあったようだ(※注2)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)『古事記』のイザナギ命(伊邪那岐命)・イザナミ命(伊邪那美命)の神話の中に、イザナミ命が死んで黄泉の国である出雲へ行くという条がある(「黄泉比良坂は、今出雲国の伊賦夜坂と謂ふ」としている。『日本書紀』では紀伊国熊野の有馬村としている)。
イザナギ命が諦めきれず、出雲まで追ってイザナミ命に御殿の戸を挟んで会う。イザナミ命の覗くなという言い付け(禁忌)を聞かず、イザナギ命が妻の姿を覗くと腐乱した死体があったという。この条は出雲の葬儀方法で追葬の一種である風葬の風習(日本では沖縄、奄美大島などのごく一部で行われている。出雲では、藤と竹で編んだ籠に死体を収め、高い山の常緑樹に吊るし、死体が腐って骨だけになってからその骨を丁寧に洗って埋葬する方法である)を思い起こさせる。
『記・紀』神話には、出雲の信仰や習俗・風習を見て取ることが出来る。これは何を意味するのであろうか? 宮廷の「旧辞」に収められていた出雲の神話をベースに、淡路島を拠点とする海人族のイザナギ・イザナミの国生み伝承などを取り入れ、新たに宮廷神話(国家神話・王権神話・天皇家神話)が作られたのかもしれない。
(※注2)十月の異名を「神無月」という。一般には、全国の神々が出雲に集い神が不在になるからとされている。これが定説となったのは十二世紀の半ばだというが、異説も多くある。一つには、世界を陰・陽の二つの原理から説く陰陽説(陰陽五行説)による説で、神は陽であり、十月は陽の気がない極陰の月とされた。
つまり「陽=神の無い月」が神無月に転化したというのである。この考え方を、具体的な神に結びつけ、神々の母であり、陰神とられるイザナミ命が(出雲で)崩御したのは十月とされ、「(母)神の無い月」というわけだ。また、神無月は「神嘗(かんなめ)月」が転化したという説である。神嘗は新穀を神に捧げる祭儀(祭礼)であるが、十月はこの神嘗のための月だったと見る説である。
神無月の由来については、この他にもたくさんありハッキリしていない。しかし、祭礼行事を見る上では由来だけではく、祭礼に対する考え(その意識の変化)を確認することも重要なようだ。実際、出雲諸社の神在祭でも、どの説を重視するかによって、祭礼の意味や起源を窺うことが出来そうである。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月30日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(六)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(六)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、お忌み祭(神在祭)(1)
旧暦十月は亥月の和名で、一般に神無月(かんなづき)と呼ばれる。それは全国の神々が出雲(※注1)に集まるからだそうだ(※注2)(※注3)(※注4)。逆に出雲ではこの月は神在月(かみありづき)と呼ばれ、出雲大社や佐太神社・神魂神社などで(※注5)、訪れた神を迎え祀る神在祭が行われる。
佐太神社の神在祭(お忌み祭・お忌みさん)では、現在月遅れの十一月二十日に神迎えが、二十五日に神送りが、三十日には止神送りが行われる(※注6)。この間がいわゆる「お忌み」の期間で、歌舞音曲は慎まれる(昔は散髪・針仕事まで遠慮して物忌みしたそうだ)。かつては出雲地方に四つある神名火山(かんなびやま)に関係する神社すべてに神在祭があったようである。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)陰陽五行説によれば、出雲は大和からは、西北の「戌亥隅」に当たる。一方、「易」の十月の卦は「全陰」だ。陽の気の象を「天」、あるいは「神」とする。すると、全陰の卦は神の不在を意味するとされている。十月はまた太陽の光りが衰微の極に近く、あらゆる点から考えて神不在とされたのだ(十一月は一陽来復が迎えられるとされた)。
出雲の佐太神社『祭典記』には、「古老が伝えていうには、此処出雲は日域(日本)の戌亥隅(西北)という陰極の地であり、女神先神伊邪那美は陰霊で、亥月という極陰の時を掌る神である。」と記している。
このことからも、出雲の旧暦十月の祭りは、祖神・伊邪那美命の追慕を名目にして参集するとも考えられた。そこからか、「神在祭」は、一名「お忌み祭り」と呼ばれる。
(※注2)神在月が成立については、平安時代末(一一七七年)の『奥義抄』に、すでに神無月の解釈として「天下のもろもろの神、出雲国にゆきてこと(異)国に神なきが故にかみなし月といふをあやまれり」とある。それ以前の成立であることは間違いないと思われる。
(※注3)神在月に出雲に集まらない神様もいる。それが留守神だ。結構この留守神伝承は各地に広がっていて、特に恵比寿、竈神、金毘羅、亥の子を留守神とする地域が多いようである。恵比寿は関東、東海地方、竈神は関東地方、金毘羅は中国四国地方を中心に分布している。
このような留守神はいわゆる神社という形で祭られる祭神ではないという特徴を持っている。ただし地域によってはこれらの神々も出雲に参集するとしているところもある。
(※注4)神無月を中心に参集する神々は氏神・鎮守系が多く、早立ちする神々は天神が多いようだ。そして最後に越年するまで滞在してしまう神々は、山の神、田の神、亥の子神、竈神等の農耕神が多いとのことである。
(※注5)神々は出雲のどこに集うのであろうか。多くの方が出雲大社に集まると思われているが、実は一ヶ所の神社に集まるのではなく出雲大社、佐太神社を中心に何ヶ所かの神社を参集して回る。
朝山神社(出雲市朝山町)、出雲大社(簸川郡大社町)、万九千社(簸川郡斐川町)、神原神社(大原郡加茂町)、神魂神社(松江市大庭町)、佐太神社(八束郡鹿島町)、朝酌下神社(松江市朝酌下町) など。
(※注6)神在月に留まる神々の滞在期間が異なる。出雲滞在期間は大きく分けて、(1)神無月を中心に参集する、(2)神無月の前に他の神より先に参集(早立ち)し先に戻る、(3)中帰りといって神無月の途中に神が一度戻る、(4)神無月から大きく離れた時期まで滞在する、の四つタイプあるようだ。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月29日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(五)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(五)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐太大神と加賀の潜戸(3)
祭祀の面からみると、佐太神社では古来より、竜蛇信仰(海蛇を神の使いとして信仰、竜蛇様)があった。竜蛇はセグロウミヘビとよばれる海蛇で背が黒色をしており、脇腹の色が金色をしている。体長は六十~七十センチの小さな海蛇だが、眼も歯も鋭く、威厳と神秘性が感じられる。
南方産のセグロウミヘビが毎年決まった頃(晩秋、日本海に北西の風が強くなる頃、出雲の海は急に暗くなり海面は荒れて泡立つ。こうした天候の急変を「お忌み荒れ」という)に季節をたがえずやって来るので古代の出雲の人々は、竜蛇様(あるいは竜神の使い)として篤く信仰していたようだ。
夜、この海蛇が海上を渡ってくるときは金色の火の玉に見えるという。そして、佐太神社の境内にある舟庫に掲げられた額には「神光照海」と書かれ、この「海を光らして依来る神」はセグロウミヘビであったと考えられる。
こうした竜蛇信仰は、海の彼方から依り来る神という古代信仰(マレビト信仰、海の果ての常世国から豊饒をもたらす神、対馬海流がもたらす南方文化への憧れと信仰)とされている。すると、佐太大神も、そうした古代出雲の海人族が信仰していた、竜蛇信仰の依来る神(竜蛇様)なのかもしれない。
また、海人族との深い関わりから、猿田彦命(猿田彦大神)とも同一視される(サタ・サダとは岬のことなのか? 猿田彦命には、縄文時代より航海の民・海人族の信仰していた、航海神・太陽神の要素が見て取れる)。
もう一つ、気になるのは「金の弓箭」のことである。矢というと類似の説話として、『山城国風土記』逸文の「賀茂の丹塗矢」伝承(賀茂建角身命の御子・玉依日売と川上から流れてきた丹塗りの矢と感けて、賀茂別雷命が生まれたとする御子神伝承)などを思い出す。
金の弓矢は雷火か太陽光を象徴しているようで、こうした説話は太陽神・雷神とそれを祀る巫女の交合の儀式(神婚説話・日光感精説話)を表しているようだ。
どうも、賀茂説話や三輪山・大物主説話との関係(類似の説話の存在は、出雲一族の大和・山城への移住と関連があるのか?)が気になるところである(柳田国男の「玉依姫考」などによると、古代信仰に共通するモチーフのようだが)。
『出雲国風土記』(嶋根郡)によると、生まれた佐太大神(または佐太御子神)は、佐太国(狭田国)の総鎮守神であり、それがカミムスビ命(神魂命)の御子(キサカヒメ命=枳佐加比売命)から生まれたとすることから、佐太大神を奉斎する氏族が神魂命を信仰する祭祀集団と何らかの関係があったことを示しているようだ。
この神魂命については謎が多いようである。カミムスビ(神産巣日神・神皇産霊神)といえば、『記・紀』では天地初発のときに生まれた独神であり、タカミムスビとカミムスビは併称されている。しかし、『出雲国風土記』では神魂命と記されており、性格は『記・紀』と異なっている。
すると、神魂命は島根半島の太古よりの、海辺の素朴な女神であったのが、本来の姿であったのであろうか? 魂を司るとする出雲土着の神の総称であったのであろうか? 神魂命の信仰については、神魂神社で一度考察してみようと思う。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月27日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(四)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(四)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐太大神と加賀の潜戸(2)
加賀の潜戸を貫いた金の弓箭(黄金の矢)とは、的島の東から射しこむ太陽の光線(黄金の矢を持つ太陽神)を比喩したものとされている(※注1)。そこから、黄金の矢を持つ太陽神が、暗い洞穴(※注2)に矢を放つとは、太陽神とそれを祀る巫女の交合の儀式と考えられている(※注3)。このような加賀の潜戸という自然の造形が、壮大な説話を生み出したのだ(本来は闇見の国の神話か?)。
さらに古代には、佐太川を境に、西を狭田の国、東を闇見(くらみ)の国と別個の小国家が成立していたようだ(国引き神話にも登場する)。ところが、この二つの国は程なく佐太大神の信仰によって繋がることになる。それは、もともと闇見の国を代表する祖神の社(久良弥社=くらやみのやしろ)があったのだが、狭田の国(佐太大神)の勢力に飲み込まれた(闇見の国の神話が狭田の国の神話に飲み込まれた)結果なのかもしれない。
すると、加賀の潜戸の説話で、「佐太大神」としているのは、実は、「佐太御子神」の誤伝で、もともと麻須羅神こそ「佐太大神」(※注4)であったのかもしれない。即ちこの説話は、古くは狭田の国の「佐太大神」が矢になって、闇見の国のキサカヒメ命(枳佐加比売命・支佐加比売命、神魂命の御子)のもとに通い、その結果として「佐太御子神」の誕生を見たとする説話であったと思われる。結果、二つの国は程なく佐太大神の信仰によって繋がることになるのだ(狭田の国が闇見の国へ勢力を伸張したことの反映)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)新潜戸から見た的島の方向は夏至の日の出の方向にあたり、反対に的島から見た新潜戸は冬至の日没の方向にあたる。夏至の朝日が生、冬至の夕日が死を象徴するものと考えられていたようだ。この説話には、神婚説話や日光感精説話が見て取れる。
(※注2)洞窟(大穴)で生まれたということで、この佐太大神とは実はオホナムヂ命(大穴牟遅命・大穴持命)のことではないかとする説もある。しかし、オホナムヂ命(所造天下大神大穴持命)を奉ずる勢力による出雲統一の以前に、この地には佐太大神の勢力圏であったようだ。神々の通い婚の説話は、オホナムヂ命に代表されるが、加賀の潜戸の説話のように佐太大神の通い婚の説話があっただ。
(※注3)元来、出雲国の佐太大神の原質は太陽神(天照神)であったのであろうか。太古より、わが国の太陽信仰は広く行われており、各地に所在する天照神(プレ・天照大神)もそうであり、大和の三輪山の山頂にも太陽神を祀る社があり、『日本書紀』(応神記)のアメノヒボコ(天之日矛・天日槍、新羅の王子)も太陽神とされている。
(※注4)佐太大神は狭田の国の祖神である。『出雲国風土記』には、この狭田の国の東部にあった秋鹿郡の神名火山の条に「所謂佐太大神の社は即ち彼の山の下也」とある。現在の佐太神社の位置からすると、きわめて不自然だ。神名火山(現在の朝日山)の下にあったのが「佐太大神の社」(神名火山の山容を仰ぎ見る地から、銅剣と銅鐸が同時に出土)で、現在の佐太神社は本来「佐太御子神の社」(神名火山の山容を仰ぐことさえできない所に鎮座)と考えたほうが辻褄が合いそうである(すんなりと解釈できる)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月26日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(三)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(三)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、佐太大神と加賀の潜戸(1)
島根半島の北の加賀の神埼には、通り抜けることのできる洞穴があって、「加賀の潜戸(かがのくけど)」(島根県八束郡島根町潜戸鼻岬の海岸洞窟。新潜戸と旧潜戸があり、旧潜戸は岬の胴体部で巨大な洞窟が広がる。玄武岩、集塊岩などが海食によりできたもの)(※注1)といわれている。
また、加賀の潜戸の近くには賽の河原もあり、幼い子を亡くした親たちが哀しみを持ってくるといわれている。この加賀の潜戸は、佐太神社の祭神「佐太大神」が生まれたとする説話が、『出雲国風土記』(嶋根郡の条などに)に残されている(いくつかの記述がみえる)。
一つは佐太大神の生まれた加賀郷の名の起こりを説いたもので、「佐太大神が生まれた所である。御祖のカミムスビ命(神魂命、神産巣日神か?、伊邪那美命か?)の御子のキサカヒメ命(支佐加比売命・枳佐加比売命)(※注2)が『闇き岩屋なるかも』といって金の弓箭(黄金の弓矢)で射たとき、光り輝いたから、加加という。神亀三年、加賀と改める。」とある。
もう一つの記載は、「加賀の神埼には窟があり、高さ約十丈、周は約五百二歩で、東西北に通じている。所謂、佐太大神の生まれたところである。生まれる時に臨み、御祖のカミムスビ命(神魂命)の弓箭(弓矢)がなくなってしまった。御祖のカミムスビ命(神魂命)の御子のキサカヒメ命(支佐加比売命)は、『吾が御子、麻須良神(ますらがみ、本来は麻須羅神が佐太大神であったのかもしれません)の御子(佐太御子神?)に坐さば、亡せたる弓箭出で来』と祈願した。そのとき、角製の弓箭が水の随(まにま)に流れ出た。『此は非(あら)ぬ弓箭なり』といって投げ捨てた。また金の弓箭が流れ出てきた。この金の弓箭を取って『闇鬱(くら)き窟なるかも』といって射通す。即ち、御祖のキサカヒメ命(支佐加比売命)の社が、この所に鎮座する。」とある。
また、佐太神社と祭神については、『出雲国風土記』には「佐太御子社」ともある(『延喜式』神名帳では「佐神社」とあり、祭神は一柱です。本来「佐太御子社(佐太御子神)」と「佐神社(佐神大神)」は別で、二社あったのであろうか? 謎である)。すると、その親神「佐太大神の社」が別に存在することになる。
もし、佐太神社の祭神が「佐太御子神」(従来、佐太神社が「秘説」としてきた主祭神を、明治になって、「佐太御子大神」と明示するようになった)ならば、『出雲国風土記』にあるように、朝日山(佐太神社の西二キロメートル)の麓に「佐太大神の社」があったことになるのだが、はたしてどうなのであろうか? (この点は複雑で難しく、その後の解釈などが加わり、多くの神々も加えられて、変化している。もう少し調べてみようと思う)
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)加賀の潜戸の近くには、加賀(かか)神社が鎮座する。祭神は、キサカヒメ命(支佐加比売命・枳佐加比売命)・猿田彦命(佐太大神)・イザナギ命・イザナミ命・天照大神である。近世には、潜戸大明神とされていた。
(※注2)キサカヒメ命(支佐加比売命・枳佐加比売命)は赤貝の神格化とされ、『古事記』には、八十神に火傷を負わされて死んだオホナムジ命(大穴牟遅命・大穴持命)を蘇生させるために、カミムスビ命(神産巣日之命)がキサカイヒメ命とウムカイヒメ命を遣わしたとある。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月25日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(二)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(二)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、出雲国二の宮
朝日山(三百四十二メートル、神名火山=神奈備山)の麓に鎮座する佐太神社は『出雲国風土記』(天平五年=七三三年)には「佐太御子社」と記され、『延喜式』(延長五年=九二七年)には「佐陀神社」と記され、「佐陀大神社」とも称せられる由緒ある古社である(この地は、出雲でも相当早い時期に人が住み着いた所で、縄文早期の佐太講武貝塚や弥生の古浦砂丘遺跡があり、はやくから農耕が芽生えていたことが窺える)。
祭神・佐太大神(または、佐太御子神)を祀り、本殿は南殿・北殿・中殿の宏大な三殿が並び、佐陀三社とも呼ばれる。古来より、出雲大社に次ぐ出雲国の二の宮と崇められてきた。
この本殿は朝日山を背に神殿が三殿並立という珍しい建て方で、豪壮な大社造になっており、国指定重要文化財にもなっている。また、祭神・佐太大神(のちに、猿田彦神と同一視されるようになる)は『出雲国風土記』における中核神であり、この神社の地位がひじょうに高かったことを示唆している。
御祭神は、北殿に天照大神、瓊々杵尊、中殿に佐太大神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、事解男命、速玉之男命 、南殿に素盞嗚尊、秘説四座が奉斎されている。
祭礼は年に七十五回行われたというが、今でも御坐替神事とお忌祭(お忌み祭=おいみまつり。社伝によれば、イザナミ命=伊邪那美命・伊弉冉尊の去った旧暦十月に八百万の神々が佐太神社に参集されるので、厳粛な物忌みがなされるところから、神在祭を「お忌み祭=お忌みさん」というとしている)が有名だ。
佐太神社の約百メートルほど東に佐太神社の摂社の田中神社がある。この神社の歴史も古く、『出雲国風土記』にその名を見ることができる。出雲地方では神無月(十月)を、全国の神々が集まるとして神在月といい、佐太神社では、十一月二十日~二十五日(旧暦十月)にお忌さん(お忌みさん)と呼ばれる神在祭が行われる。
毎年、九月二十四日には神座に敷く御座を敷き替える御座替神事が行われ、翌日に奉納される佐陀神能は、神楽に能の舞を取り入れたもので深夜まで続く(国の重要無形民俗文化財)。
佐太神社では古来、竜蛇(海蛇を神の使いとして信仰する竜蛇信仰)は恵曇の古浦から上がるとされていた。古浦とそのとなりの江角浦とを合わせて神在浜と呼ばれるが、そこには板橋という佐太神社の社人が居住して、松江藩から食禄を受け、竜蛇上げの職を奉していたといわれている。
竜蛇はセグロウミヘビとよばれる海蛇(背が黒色をしており、脇腹の色が金色をしている)で、この海蛇が海上を渡ってくるときは金色の火の玉に見えるという。
そして、佐太神社の境内にある舟庫に掲げられた額には「神光照海」とかかれ、「海を光らして依来る神」はセグロウミヘビであったと思われる(お忌み祭の頃の季節風=お忌み荒れによって浜に打ち上げられる。こうした竜蛇信仰は、海の彼方から依来る神という古代信仰である)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月25日
◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(一)

◆島根県八束郡・佐太神社の御座替神事(一)
◆◇◆島根県八束郡・佐太神社、御座替神事
九月二十四日と二十五日に、島根県八束郡鹿島町の佐太大社で、かがり火と灯明がともる中、御座替神事が厳かに営まれる(九月二十四日に御座替神事を行い、翌二十五日に佐陀神能を行う)。
この御座替神事は、同社の古伝祭の一つで、神在月(陰暦の十月に日本全国の神様が出雲に大集合して会議をするという)に先だって、神殿内陣の神座のござ(御座)を新しく敷き替える行事である(摂社末社から正中殿に至るまで順々に御座を敷き替えて、二十五日に幣帛を祀ってお祝いをする)。このことにより、神々の力が常に新しく続くと考えられた。
九月二十四日午後八時から行われた神事では、神職らが二十一ある末社から南殿・北殿・本殿の順に、宍道湖北岸で栽培されたイ草で作った新しいござに敷き替えていく。
舞殿では、神事に合わせ、出雲神楽の源流といわれる佐陀神能(神楽に能の所作を取り入れたもの、国の重要無形民俗文化財に指定)の「七座の舞」(鼕-どう-や笛などの音に合わせ古式ゆかしく行われる優雅な舞)を奉納した。
この神事は、神在月には全国から神様が集まって来るので、神座のござ(御座)を新しく敷きかえて、きれいにしておこうというものである。もう千二百年年以上続いている、古式ゆかしい神事だ。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月23日
◆秋分の日と秋の彼岸の中日(四)

◆秋分の日と秋の彼岸の中日(四)
◆◇◆皇室の祭祀、大祭と小祭
皇室の祭祀において、神武天皇と先の天皇の祭祀は大祭、それから三代前までの天皇の祭祀は小祭として行われる。また、それ以外の皇祖(皇室の御祖先)については、年に二回、春と秋に「皇霊祭」として行われる。歴代天皇すべての天皇について個別に祭祀を行っていては、却って疎かになってしまうかもしれないということで、このような形がとられるようになったそうだ。
これらの皇室の祭祀はすべて宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)の中の皇霊殿で行われる。また、神武天皇祭、孝明天皇例祭、明治天皇例祭、大正天皇祭、昭和天皇祭については墓所でも祭祀が行われる。
◆◇◆春季皇霊祭・秋季皇霊祭
明治維新は政治的にも武家の政治(江戸幕府)を終焉させ近代民主国家への道を切り開くものであったが、宗教界にも大きな変革を強要した。その中心が江戸時代にキリスト教対策で重視されていた寺を排斥・弱体化(神仏判然令・廃仏毀釈運動)させるとともに、明治維新の原動力(尊王攘夷運動と王政復古の波、平田学と後期水戸学)の一つとなった国学(本居宣長・平田篤胤など)の流れを汲む国家神道を樹立して、全国の神社を皇室に縁の深い伊勢神宮を頂点とするヒエラルキーに組み込もうと計った(近代社格制度の整備とは、伊勢神宮をトップとした神社のランク付け)。
この動きはいわば皇室の神道の普遍化(国家神道は、天皇の宗教的権威の中心に皇室神道と神社神道とを直結し、皇室の祭祀を基準に神社の祭祀を画一的に再構成すること)を狙ったものともいえるが、そのため初期の段階では歴代の天皇の命日を全て新暦に換算した上で、その命日すべてをお祀りする(祭祀儀礼をする)、という企画が立てられた。
しかし天皇といっても初代神武から、明治天皇の先代の孝明天皇まで百二十一代に及んでいるので、これを全て命日のお祀りをするのは、実際やってみると非常にたいへんことであった。そこで明治政府は早々にこの方法に根を上げて、結局神武天皇の命日(四月三日)と孝明天皇の命日(一月三十日)のみを残して、あとは民間でも先祖供養の日としている春・秋のお彼岸に春季皇霊祭・秋季皇霊祭としてまとめてお祀りすることになったものだ。
春季皇霊祭・秋季皇霊祭は明治十一年に祝日として定められ太平洋戦争の終わりまで続いた。戦後の春分の日・秋分の日は戦前のそういう趣旨は排除した上で、もともとの民間の先祖供養の日としての趣旨のお彼岸を復活させたものである。春季皇霊祭・秋季皇霊祭は宮中行事・皇室の祭祀として行われる。
宮中行事・皇室の祭祀の春季皇霊祭・秋季皇霊祭は、三月の春分の日と九月の秋分の日(彼岸の中日)に、天皇家の祖先を崇める祭りである。天皇が皇霊殿で玉串を捧げて拝礼し、告文を奏する。続いて、神殿でも親祭が行われる。皇霊殿では「東遊(あずまあそび)」と呼ばれる雅楽が奉納される。
◆◇◆皇室祭祀
明治十四年に制定された「皇室祭祀令」に基づいて行われる。大祭と小祭に分けられ、大祭は天皇自らが行い、小祭は掌典長(しょうてんちょう)(天皇家の私的内廷組織)が指揮する。天皇はそれに拝礼する形をとる。皇室祭祀は、主として吹上御苑(ふきあげぎょえん)にある宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)で行われるが、先帝を祀る山稜でも行われる。戦前は、こうした祭祀には総理大臣はじめ多くの参列者があったが、昭和二十年の「政教分離」により、今では天皇家の私的行事の色彩が濃くなっている。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月23日
◆秋分の日と秋の彼岸の中日(三)

◆秋分の日と秋の彼岸の中日(三)
◆◇◆春季皇霊祭・秋季皇霊祭(こうれいさい)と宮中行事、皇室の祭祀
宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のひとつ、皇霊殿には、歴代天皇・皇族方の御霊がお祀りされている。明治以前は、仏式により寺院や宮中のお黒戸に霊碑を奉祀しされちたが、明治天皇は、これを神式に改められ、皇霊殿において春秋ニ季の皇霊祭を行うことを制定された。
春分・秋分の日は彼岸の中日として、古くから先祖の御霊を祀る日とされていたが、明治十一年に明治天皇がこの日を皇霊祭の祭日に定められたことにより休日となり太平洋戦争の終わりまで続いた。
現在では、戦後の春分の日・秋分の日は戦前のそういう趣旨は排除した上で、もともとの民間の先祖供養の日としての趣旨のお彼岸を復活させたものである。皇室では、春秋ニ季の皇霊祭は宮中行事・皇室の祭祀として現在に至っている。
◆◇◆春秋ニ季の皇霊祭(宮中行事)は、祖先供養の風習を仏教色をのぞいて宮中行事化したもの
春分の日(三月二十一日頃)と秋分の日(九月二十三日頃)、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」と「先祖をうやまい、亡き人をしのぶ」ということで、日本の仏教では、平安時代のころから春秋に彼岸会(ひがんえ)が催され、悟りの彼岸へ至るための法要が営まれていた。また浄土思想の広がりとともに、彼岸の中日(ちゅうにち)の夕刻、落日に向かって念仏を唱えれば、西方の極楽浄土に往生出来ると信じられていた。
しかし本来祖霊崇拝の思想は仏教にはなく、日本古来の風習が仏教と習合したと考えられている。明治以来宮中で行われる春秋ニ季の皇霊祭は、祖先供養の風習を仏教色を除いて宮中行事化したものにほかならない。春分・秋分の日の趣旨は、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」と「先祖をうやまい、亡き人をしのぶ」という日本本来の自然観に立ち返ったものといえる。
◆◇◆春季皇霊祭・秋季皇霊祭と皇室の祭祀
「春分の日」「秋分の日」は皇祖皇宗を祀る「春季皇霊祭」「秋季皇霊祭」の日である。皇祖とは天照大神から初代の神武天皇までの皇室の祖先で、 皇宗とは第二代天皇以降の歴代の天皇のことだ。
戦前に春分には「春季皇霊祭」、秋分の日には「秋分の日」が行われ、つまり皇室のお彼岸であってだ。これが宮中行事化していったのである。他にも以下のように、皇室の皇祖皇宗を祀る祭祀は年に七回行われている。
1月7日 昭和天皇祭 (大祭) 昭和天皇崩御日に行われる
1月30日 孝明天皇例祭(小祭) 孝明天皇崩御相当日に行われる
3月21日 春季皇霊祭 (大祭) 皇室の御祖先祭神殿では「春季神殿祭」が行われる
4月3日 神武天皇祭 (大祭) 神武天皇崩御相当日に行われる
7月30日 明治天皇例祭(小祭) 明治天皇崩御日に行われる
9月23日 秋季皇霊祭 (大祭) 皇室の御祖先祭神殿では「秋季神殿祭」が行われる
12月25日 大正天皇祭 (小祭) 大正天皇崩御日に行われる
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月22日
◆秋分の日と秋の彼岸の中日(二)

◆秋分の日と秋の彼岸の中日(二)
◆◇◆秋分の日とお彼岸、日本のしきたり
毎年、春分の日と秋分の日の事を民間では「お彼岸」(※注1)(※注2)といい、お墓詣りをして先祖の霊を供養したりする。今年(2006年)の秋分の日は九月二十三日だが、民間行事のお彼岸ではこの日を「お彼岸の中日」といい、その前後一週間をお彼岸の期間として最初の日を「彼岸の入り」最後の日を「彼岸の明け」という(秋分の日をはさんで前三日、後三日、合計七日が彼岸)。
「国民祝日に関する法律」によると、「春分の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」、「秋分の日」は「先祖をうやまい、亡き人をしのぶ」とある。まさに仏教の精神そのものだ。この日は、太陽が真東から昇り、真西に沈み、昼と夜の長さが同じになることから、仏教で説く中道も表しているという説もある。
またこの時期には、、旧暦八月酉の月の中気で、お彼岸の中日でもある。真西に日が沈むこの日、西方に浄土があるという仏教の教えから、無欲吾道の対岸の域に一番近くなる日ということで、死者の冥福を祈り、仏供養、お萩(ぼたもち)、草餅、五目ずし、稲荷ずしなどを作ってお墓参りをする習慣がある。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)彼岸とはその名の通り「大きな川を挟んだ岸の向こう」という意味である。その向こう岸とは悟りの世界(仏の世界があり、私たち凡夫はこちらの岸・此岸にいると考えている)のことだ。
サンスクリットでは、パーラミター(波羅蜜多)という。様々な苦に悩む煩悩の世界(私たち凡夫はこちらの岸・此岸)に対する言葉であるが、日本の特に浄土系の信仰では一般に死後は阿弥陀如来の導きにより人は彼岸に渡ることができると考えられているため、既に彼岸の世界へ行った人達を供養するとともに、まだ辿りつけずにいる人達に早く向こうへ辿りつけるように祈るというのがこの彼岸の仏事の趣旨となる。
お寺ではこの一週間法要を続け、住職が檀家を回って各家庭でも法事を行う。この時期に彼岸の法要を行うのは、太陽が阿弥陀如来のいる浄土の方角である真西に沈むためであるともいわれている。つまり阿弥陀浄土を感じるのに最適であり、迷っている人にとっては太陽の方角が進むべき道ということになる。
このように、現世と浄土との間に川があると云う比喩は、中国の唐の時代の善導(六一三~六八一)が『観経疏』散善義において「二河白道(にがびゃくどう)」の喩えによって絵解き的に述べたものが我が国にも伝わり、これが平安時代に浄土教の普及とともに広まっていったものであるとされている。
(※注2)戦前、我が国では、この彼岸会の日を春季皇霊祭、秋季皇霊祭と呼んで、皇室がその祖先を祀った(太陽暦の導入に伴い、それまで宮中で行なっていた皇祖=天皇の祖先を祀る行事もすべて太陽暦に換算することとなる。しかし、あまりに量が多いため、春季皇霊祭と秋季皇霊祭にまとめて行なうこととなる)。
国民の祝日として、明治十一年(一八七七年)から昭和二十二年(一九四七年)年まで実施。今でも、宮中では春季皇霊祭・秋季皇霊祭が行われ、神武天皇(じんむてんのう)をはじめ歴代天皇・皇族の御霊(みたま)がお祀りされる。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月22日
◆秋分の日と秋の彼岸の中日(一)

◆秋分の日と秋の彼岸の中日(一)
◆◇◆秋分の日とお彼岸、「暑さ寒さも彼岸まで」
秋分の日(Autumnal Equinox Day) は、春分の日(三月二十一日頃)と同じく、太陽が真東から出て真西に没する日である(※注1)。 このため、昼と夜の時間が等しくなる(太陽が赤道上にあり、昼夜の長さが等しくなる)。これより徐々に昼が短く、夜が長くなっていきます(九月は長月=ながつき=夜長月といい、夜が長くなる月なのでそう呼ばれる)。
秋分の日は大体九月二十三日頃にあたり(今年は、九月二十三日)で、また秋の彼岸の中日(※注2)でもあり、国民の休日(※注3)にもなっている。近年は温暖化の影響でまだ暑さの残る気候だが、かつては暑くもなく寒くもないさわやかな時節とされ、「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるように暑さも峠を越し、過ごし易い気候になる。また、収穫と秋祭りの時期でもある。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)秋分とは、天文学的には、太陽の黄経が180度になった瞬間をいう。つまり、黄道(太陽の通り道)が天の赤道(地球の赤道を天球上までのばしたもの)を横切る交点に太陽がきた瞬間のことである。秋分の瞬間を含む日を秋分の日という。
秋分は黄道上の太陽の位置によって定まる二十四節気の一つで、旧暦八月酉の月の中気である。秋分の日には、全国で収穫と秋祭りは行われる。また、「暑さ寒さも彼岸まで」という言うように暑さも峠を越して温和な気候になる。
(※注2)彼岸は、春分の日(三月二十一日頃)と秋分の日(九月二十三日頃)をはさんだ前後の三日間ずつ、計七日間のことで、それぞれ春彼岸、秋彼岸といい、彼岸の最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸の明け」、春分・秋分の日を「彼岸の中日」といいう。
彼岸には、お墓参りをする習慣があり、祖先の霊を家に迎える盆とは違って、祖先に会いにゆく行事としての色彩が濃いようだ。しかし、仏教に由来する行事と考えられている彼岸は、日本にしかない行事で、豊作に欠かすことのできない太陽を祀り、祖霊の加護を祈る古くからの儀礼と結びついたものといわれている。
(※注3)春分の日および秋分の日は国民の祝日であり、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)によると、「春分の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」、「秋分の日」は「先祖をうやまい、亡き人をしのぶ」とあり、それぞれの年の春分日および秋分日にすると定められている。
春分日・秋分日は毎年変わるので、前年の二月一日付けの官報で日本国政府から発表されることになっている。したがって、再来年の春分の日および秋分の日は来年の二月一日にならないと正式には分からないことになる。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月19日
◆秋分の日と秋行事・彼岸の中日(序)

◆秋分の日と秋行事・彼岸の中日(序)
◆◇◆秋分の日と秋の行事・彼岸の中日
彼岸とは、雑節の一つで春・秋2期の彼岸会(ひがんえ)のことだ。春分の日・秋分の日をはさんで前後三日ずつ、計7日間をいう場合もある。 彼岸の初めの日を「彼岸の入り」といい、 終わりの日を「彼岸の明け」、また春分・秋分の日を「彼岸の中日」という。
彼岸の入りから四日目が彼岸の中日になる。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉を耳にするが、彼岸は季節の変わり目であり、寒暑ともに峠を越す。
彼岸の間、各寺院では彼岸会の法要が行われる。彼岸は本来仏教用語でサンスクリット語のpara(波羅)の訳で、「到彼岸」という語に由来している。生死輪廻の此岸(しがん、煩悩に満ちた世界)に対してそれを解脱した悟りの境地(涅槃・悟り)の世界に至るという意味である。
さらに煩悩に満ちたこちらの世界を現世、涅槃の世界を死後の極楽浄土と捉え、あちらの世界と考えたところから、亡くなった先祖達の霊が住む世界を「彼岸」と考えるようになりました。
秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈む。そして涅槃の世界を「西方浄土」と呼ぶ事があるとおり、阿弥陀仏のいる極楽浄土は「西」にあるとされているので、真西に太陽が沈む春分の日・秋分の日は夕日が極楽浄土への道しるべとなると考えられたのだ。
また、昼と夜の長さが等しいので、仏教を尊ぶ中道の精神にかなったという説もある。仏教的色彩の濃い彼岸であるがインドや中国にはみられない、日本独特のものといわれている(彼岸会の始めは大同元年=806年、崇道天皇=早良親王の霊を慰めるために行われたとも)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月18日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(八)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(八)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、「物語の出で来はじめの祖(おや)」
『竹取物語』(通称「竹取物語」、「竹取翁の物語」とも「かぐや姫の物語」とも呼ばれてきた)は、『源氏物語』絵合巻(絵合せの帖)に「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」と称揚された、初期物語の代表的秀作であり、日本最初の「物語」(「昔話」など口承・伝承的なものではない作り物語‘’伝奇物語 。しかし、作者や年代を含めてその成り立ちは未だ謎)だとされている。
日本人なら誰にでもそのあらすじを知っている、我が国古典文学を代表する作品でもある。作者、成立に関わる確かな記録は残されておらず、『大和物語』にこの物語にちなんだ和歌が詠まれて以降、『宇津保(うつほ)物語』の女主人公「あて宮」の造型に強い影響を与えたほか、『源氏物語』にも多くの「かぐや姫」的な女性たちが登場するなど、後の物語文学(十一世紀成立の『栄華物語』や『狭衣物語』や十二世紀成立の『今昔物語集』など)への影響ははかりしれないものがあったようだ。
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、作者・成立年代未詳
『竹取物語』の書名、作者、成立、書誌、伝本には多くの謎(確かな記録は残されておらず)があり、未だにその全貌は明らかにされていない。特に、かぐや姫の誕生の場がなぜ「竹」であるのか、ということについては、隼人(海人族・海神族・南九州)の竹文化(竹民俗)との関連も指摘されているが、確固たるところは不明だ。
『竹取物語』の作者については、『竹取物語』の文体・語彙・語法・構成・難題の品などから、和歌に秀で、中国などの仏典、漢籍に深く通じ、大陸文化に造詣の深い教養人で、古来の伝承をもとにして文学的にまとめ上げるこのとできる人物と考えられている。
古くは「紀貫之(きのつらゆき)『土佐日記』」や「源融(みなもととおる)三十六歌仙」、「源順(みなもとのしたごう)『後撰集』」。書き出しの類似から「源隆国(みなもとのたかくに)『今昔物語集』」、和歌の作風から「僧正遍照(そうじょうへんじょう)六歌仙」、漢文体『竹取物語』から「空海(くうかい)」などが取り沙汰されてきた。したがって、成立年代も特定できない。
およそ『白氏文集(はくしもんじゅう)』伝来の承和(八四七年)以後、和歌の歌風から貞観(じょうがん)年間(八五九~八七六年)、さらには『古今集』撰進前後の延喜五年(九〇五年)あたりまで、諸説入り乱れているというのが現状だ。
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、『竹取物語』とかぐや姫、物語の構成要素と構造
この物語『竹取物語』にはさまざまな要素が盛り込まれているが、「竹取の翁」が竹の中から幼子を発見(竹中生誕譚)し、富を得るという致富譚(ちふたん、貧者が長者になる説話)や、「かぐや姫」が三月で成人するという急成長譚、求婚難題物と求婚者たちの名前に密接な関連を持たせながら、それら難題求婚譚の顛末を語りつつ、その最後に巧みなラストシーンが用意されている語源譚、さらに御狩の行幸・帝の求婚譚、かぐや姫の昇天譚(羽衣説話)、ふじの煙(地名起源説話)と続く構成要素と構造など、古物語の体裁を装いながら、実は古代小説の始発に位置する作品として完成度の高い内容を誇っている。
かぐや姫の誕生(竹中生誕説話)→ 竹取翁の長者譚(致富長者説話)→ 妻どい・五人の貴人の求婚(難題求婚説話)→ 御狩の行幸・帝の求婚譚→ かぐや姫の昇天(羽衣説話)→ ふじの煙(地名起源説話)
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月15日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(七)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(七)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月は不死の世界(神仙思想)
日本人であれば、月と兎と言えば、餅つきが連想さる。また、中国では兎は不死の薬を搗き、月は不死の世界とされた(※注)。月は新月と満月を繰り返し、一度消えて復活することから、古代人は不死を感じたようである。日本でも、『竹取物語』には、月に不死の薬があるとされている。
かぐや姫は昇天の際、月世界に戻るため不死の薬を少し嘗め、残りを翁に渡す。翁は天皇に献上するが、天皇も不死の薬など要らぬと言って、名前も不死の山(富士山)で燃やして天(月世界)に返してしまった。この話は、人は不死を拒否したとの譬えにも取れる。
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、満月とかぐや姫
「かぐや姫」という名は、「光り輝くヒメ」という名義である。これは第一に満月時の月光の謂いであろうと推察される。すなわち、満月信仰や観月民俗が「かぐや姫」誕生の前提にあったようだ。
『竹取物語』で、翁はかぐや姫を竹筒の中に発見する(『塵袋』には、竹の中に住む兎が隠岐島へ洪水で流される話が見られる)。かぐや姫や兎が竹と係わるのは、竹筒などの閉塞された空間が、神などの不可思議な存在が出現する聖なる空間であるとする考えがある(竹そのものにも驚異的成長力から、古代の人々は神秘的な力を感じていた)。
また、竹筒は、下から月を見るように見上げれば、円に見え、満月も円であることとする見方もある。また、月の斑点は一般的には兎とみる見方があるが、一方女性に見る見方も少なくない。かぐや姫はその光り輝く名義からも、月中の斑点に見出した美女が原型かもしれない。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注)中国の信仰や習俗の底流(基層)には、中国神話と原始宗教(人類に普遍的な豊穣と再生の信仰)が見え隠れしている。中国思想は、東洋の合理的な儒教や現実主義的な道教を第一に考えてしまうが、こうした思想が中国全土を覆い尽くす以前は、非合理的で呪術的で神秘主義的なもう一つの中国があったのである。
そうした失われた太古の中国の痕跡が近年盛んに発掘され、ようやく解明の糸口が見えるようになってきた。その一つが長江流域の「長江文明(総称)」である。上流域の四川省の三星堆(さんせいたい)遺跡もそういった文明の一つだ。
中国神話では、月で不死の薬草を搗く兎の説話は、西王母(せいおうぼ、西方の仙界・崑崙山に棲むという)の神話に属し、仙界の一つが月世界であった(蓬莱山なども)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月14日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(六)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(六)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月神・ツクヨミ命(月読命・月夜見尊・月弓尊)
『記・紀』の神代には、父神・イザナギ命(伊邪那岐命・伊弉諾尊)の左目(陽)から太陽神・アマテラス(天照大御神・天照大神)、右目(陰)から月神・ツクヨミ命(月読命・月読尊・月夜見尊・月弓尊)(※注1)が生まれたと記されている(ちなみに、スサノヲ命は鼻から生まれたと『古事記』)。このように、日月は父神・イザナギ命の両眼として描かれている。
そして、『古事記』では、父神・イザナギ命から、「汝命は、夜の食国を知らせ」と命じたとあるが、『日本書紀』(一書・第六)には、「月読尊は滄海原(あおうなばら)の潮の八百重を治すべし」とある。この話からは、海を主な生産の場とする海人族の信仰と月神との結び付きを感じさせる。
月読命(ツクヨミ命)の「ヨミ」は月の満ち欠けを読むことから、ツクヨミ命は暦日を読むことと吉凶を占う(農事を占う)ことに関係し、さらに潮汐を司る神ともされ、月と潮の満干にも関係しているとされている。以上のように、ツクヨミ命は農耕と深く関係する神であり、また航海とも関係する神でもあったわけだ。
『記・紀』神話の中では、月神・ツクヨミ命は、穀物神・ウケモチ神(保食神)のもてなしの仕方が汚いと言って斬殺するが、殺されたウケモチ神(保食神)の体から、栗・稗・稲・麦・大豆・小豆等の穀物の種が穫れる(穀物起源神話、その他にも牛・馬・蚕など)。
これは、穀物の死(刈取り)と種子の誕生(収穫)という死と再生(復活)が、月神と深く係わることを示す神話である(月の満ち欠けする様と、死と再生の反復を重ねて見ていたのであろう。これは、太古から人々が月に対して持ち続けていた月の神秘のイメージである)。
そうした考えが、生命の源泉である水と結びつき、日本では古くから月神が若返りの水(魂を若返らせる霊力の水)をもたらすとする信仰が生まれた(正月の若水汲み、東大寺二月堂のお水取り、穢れを祓う水)。
『万葉集』には「天橋も 長くもかも 高山も 高くもかも 月読(つくよみ)の 持てる変若水(をちみず) い取り来て 君に奉りて 変若(をち)得しむもの」(天の橋がもっと長いなら、高山がもっと高いなら、月の神の持っている若返りの水を取ってきて、あなたにさしあげて若返らせてあげるのに)(巻十三・三二四五)と若返りの水の伝承が歌われており、この神が生命力への信仰と深い関わりを持っていたのであろうことが推察される。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)月神・ツクヨミ命は、黄泉の国から戻ったイザナギ命が、禊祓をして生まれた三貴子の一柱である(世界の神話では、太陽神は男神で、月神は女神とされるが、日本の神話では反対である)。アマテラス、スサノヲ命と兄弟神になる。『記・紀』神話では、太陽信仰のアマテラスを中心とした神統譜が作られたので、月神・ツクヨミ命の存在は薄くなってしまった。
しかも、ツクヨミ命に関する神話はほとんどなく、『日本書紀』に、ウケモチ神(保食神)が口から穀物・獣などを出してもてなそうとしたのを見て「きたないことをする」と言って殺してしまったとしている。それに対して、アマテラスは「悪しき神なり」とツクヨミ命の所行に怒り「もうお前には会いたくない」と言ったとしている。
そのため月は太陽の出ていない夜にしか輝くことができなくなり、太陽と月は昼と夜に別れて輝くようになったとする「昼夜起源」説話とされるのである。ただし、この説話は『古事記』ではスサノヲ命がオオゲツヒメ神(大気都比売神)を斬殺したことになっている。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月13日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(五)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(五)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、古代の月と祭り
古代(太古の昔より)、人々にとって、祭りは互いの連帯を強め、地域や集落の結束を固める上で、とても重要な行事であったと想像でる。なかでも、先祖を祀る祭りと自然の恵みに感謝する祭りは、地域や集落の一大イベントであったのであろう。共通の先祖を確認することによって、互いの同胞意識(連帯感)を高めたに違いない。そして秋の収穫が終わると、祭りはピークを迎えるのだ。
酒(果実酒)が振る舞われると、人々は夜通し歌い踊り、そして恵みをもたらした自然の神々に感謝するのである。そしてその次の年もよき年であるよう、豊饒を祈願する「神祭り」を行った。その際、空には大きな満月が煌々と光り輝いていたはずである(※注1)。それは古代(太古の昔より)において、毎月の満月が特別な節目(祭り、ハレ)であったのだ。当時の月は今よりも空気が澄んでいる分大きく、くっきりと鮮やかに、自分たちを包み込むように見えたのであろう。
少しずつ欠けていく月(※注2)は、厳しい冬の到来がそこまで来ていることを知らせてくれた。だからこそ、秋の満月の夜には不安をかき消すかのように、人々は酒を飲み、夜通し歌い踊りあかしたのであろう。その名残が、「芋名月」や「豆名月(栗名月)」として受け継がれてきているのである(月祭り、満月信仰、観月民俗)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)古代(太古の昔より)、月が全く出ない夜というのは、恐ろしい物の怪(鬼や魔物)の住む闇の世界であった。闇夜は、古代人にとって何よりも怖いものであったのである。そうしたとき、人々は一所に集まり、一晩中騒ぎまわって闇の恐ろしさを紛らわしたのであろう。それだけに明るい月が上って、煌々と住居の中まで照らしてくれる夜は、どんなにか人々の不安をかき消し、心を安らげたことであろうか。
(※注2)月は規則的に満ち欠けし、その周期的な運動は何かの霊威を、人間や大地に確実に照射しているかのように感じ取れる(感じ取られていたのであろう)。古代、月の満ち欠けは、月の「死と再生~満月~死と再生」という、死と再生をくり返す姿と捉えられていたのだ。そして、その月の霊威の最盛期が満月の夜であったのである。古代の人々は、満月の夜、世界と人間のすべては月の最大の生エネルギーを浴びると考えた。これが本来の月見だったのである。(月祭り、満月信仰、観月民俗)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月12日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(四)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(四)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月祭り(陰暦九月十三日)
陰暦九月十三日には宵から姿を現わす月のもと、秋の収穫を神々に感謝する月祭り(月を祀る神祭り)が行なわれ、酒を神と酌み交わして楽しむ風習が生まれた。中国では古来、陰暦八月十五日を「仲秋節」とし「観月の宴」を催していた。
これが奈良・平安期の日本に伝わり、宮廷では陰暦八月十五日の夜の「仲秋の名月」と、陰暦九月十三日の夜の「月祭り(月を祀る神祭り)」と、二つの月見が催されるようになった。
種々の供物を供えて名月を賞で、月見酒を酌みながら、詩歌管弦、舞楽、歌合せなどを行い、あるいは風流な前栽(せんざい=庭の植え込み)をつくり、広大な池泉に船を浮かべて月見をするなど、洗練された風雅な遊びと化していった。
鎌倉・室町時代になると武士が台頭し、庶民も次第に力をつけるようになって、月見の風習は武家や庶民へとひろがり、再び古代の農耕儀礼(※注1)と結びついた風習に返っていったようである。
たわわに稔った稲の初穂(これが後にススキに変わったといわれている)、里芋、枝豆、団子と共に、新米で醸した酒を供え、神々に豊作を感謝し、月見酒を神と酌み交わす行事が定着した。その後、月が出る前に空が明るくなる「月白(つきしろ)」は、仏達の御来迎だと考えられるようになった(※注2)。
また、いにしえの日本人の月に寄せる想いは熱く、たくさんの美しい言葉を生み出した。十五夜への期待がふくらむ前夜は「待宵(まつよい)」、月は「小望月(こもちづき)」、待ちに待った当夜、雨や雲で見えないことを「雨月(うげつ)」「無月(むげつ)」などと称し、日毎に表情を変える月の風情を愛でてきた。
こうした風情は、「月々に 月見る月は 多けれど 月見る月は この月の月」(中秋の名月がすばらしいのは、秋になると空気が乾燥し、月が鮮やかにみえるからだ)などといって月は古くから詩吟や俳諧の題材にもされてきた。
さらに、十五夜から日がたつにつれて少しずつ欠けてゆく月を神聖視し、次第に遅くなる月の出を、十五夜の次の月は「十六夜(いざよい)」、十七夜の月を「立待(たちまち)」、十八夜の月を「居待(いまち)」、そして十九夜の月は「寝待(ねまち)」または「臥待(ふしまち)」、二十夜の月は「更待(ふけまち)」・・・、また二十三夜の月「二十三夜待」と続く。
このように、ひたすら月を待つしきたりが生まれた。「十三夜」は、翌月の陰暦九月十三日の月をいい、枝豆や栗を供えてお月見する、最後の名月である。こうして日本人は自然と心を通わせ合い、宴(風雅な遊び)を楽しんできたのだ。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)暦のない昔は月の満ち欠けによっておおよその月日を知り農事を行なっていた。そこで、十五夜の満月の夜は祭儀の行なわれる大切な節目でもあった。地方によっては稲穂を供える「稲草祭」や新しく採れた芋を供える「芋名月」などの風習もあり、農民の間では農耕行事と結びついて収穫の感謝祭としての意味も持っていた。特に芋(里芋)を供える風習は、それが主食だった縄文時代にまで遡るといわれている。
(※注2)民俗学者の折口信夫は「お月見に信仰の意味合いがあるのは、月が出る間際の空のほのかな明るみ(「月白(つきしろ)」)に、左右に観音・勢至両菩薩を従えた阿弥陀如来の来迎を拝することができると信じたから」と考えていた。夜が更けて出る月を神聖視して、陰暦八月十五日の月「十五夜」を一番としたが、前夜、陰暦八月十四日の月を「待宵(まつよい)」、満月の翌日の月を「十六夜(いざよい)」などと称して信仰と観賞の対象とした。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月11日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(三)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(三)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、十五夜「芋名月」と十三夜「豆名月」
仲秋の名月の日、全国各地の神社では、秋の風情を楽しむ観月祭(かんげつさい)が行われる。また、十五夜に次いで月が美しいといわれた十三夜 (旧暦九月十三日) にも、月見の宴が催された。里芋とつながりのある十五夜を「芋名月」と呼ぶのに対し、豆、栗の収穫時期と重なる十三夜を「豆名月」、「栗名月」ともいい、これらはお菓子の銘にもなっています。なお、「片見月 (かたみづき) 」といって、十五夜だけを鑑賞して、十三夜を見ないことを忌む考え方も江戸時代後期には見られた。
秋は無事に育った稲を収穫する喜びの季節である。各地の神社では、秋の収穫を感謝する秋祭りが行わる。秋祭りでは、その年初めての新穀=初穂(はつほ)を神さまに感謝の気持ちを込めてお供えする。神さまへのお供物を初穂と総称するのはこのことに由来する。これから全国で、秋祭りが行われていく。
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、満月と祭り、満月信仰と観月民俗
月見については、いまでは中秋のものだけが特別扱いされるだけだが、もともとは毎月の満月が特別な節目(祭り、ハレ)であったようだ。旧暦一月十五日に小正月というものがあるが、実は元旦の正月は官製のもので、民衆レベルでは小正月こそが正月である。民衆レベルでは毎月の中心は満月の夜であったのだ(古来より、月見は毎月の「小さな」正月であった)。
古代、月が全く出ない夜というのは、恐ろしい物の怪(鬼や魔物)の住む闇の世界であった。闇夜は、古代人にとって何よりも怖いものであったのである。そうしたとき、人々は一所に集まり、一晩中騒ぎまわって闇の恐ろしさを紛らわしたという。
それだけに明るい月が上って、煌々と住居の中まで照らしてくれる夜は、どんなにか人々を安らげたことであろう。月の満ち欠けを暦代わりにして農耕を営んでいた古代人にとって、月は農耕の神として信仰の対象であり、月に寄せる想いは今日の私たちが考える以上に深いものがあったようだ。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月10日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(二)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(二)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、名月を観賞する習慣、古来からの農耕儀礼
仲秋の名月(旧暦八月十五日)には、各地でお月見の行事(すすきや団子などを供え月を観る行事)が行われる。仲秋とは八月のことで、満月が十五日にあたる(※注1)。古来中国では、十五夜を「仲秋節」と称し、月餅(げぺい)などを供えて月見をする風習があり、それが奈良時代にわが国に伝えられたとされている。平安時代、貴族の間では十五夜の満月をめでつつ詩歌や管弦を楽しむことが盛んになった。次第に武士や町民へと広がっていった(※注2)。
しかし一方では、中国から伝わる以前に、わが国独自の農耕儀礼が行われていたという説もある。暦がなかった時代(この行事の起源はかなり古く)、農事は月の満ち欠けによって進められ、なかでも最も大切な節目とされた十五夜(陰暦八月十五日の満月)には、稲作が伝わる以前からよく食されていた里芋の収穫の感謝祭などが行われていた。元来は豊作の象徴である満月に秋の七草や団子、季節の野菜などを供えて、月を祭る神祭りの日であったと考えられている。
団子は、古くは日本の代表的食物で、ちょうどこの頃出る里芋を炊いて供えたのが原型とされ、秋の名月を今でも「芋名月」と呼びならわし、里芋などを供える地域が多いのは、その名残といわれる。現在、関東の丸形のだんごに対し、関西では里芋形のだんごが供えられるのも、月見の古い形態にちなんだもののようだ。また、すすきの穂を供えるのは稲穂の変化した形ともいわれている。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)一年には「春夏秋冬」の四季があるが、旧暦では三ヶ月毎に季節が変わり、「一・二・三月」は春、「四・五・六月」は夏、「七・八・九月」は秋、「十・十一・十二月」は冬となる。そしてそれぞれの季節に属する月には「初・中(仲)・晩」の文字をつけて季節をさらに細分するのに使った。
たとえば旧暦四月は「初夏」となる。このように当てはめると、「八月」は秋の真ん中で「仲秋(中秋)」となる。旧暦は太陰暦であるから日付はそのとき月齢によく対応しますから、月の半ばである十五日はだいたいにおいて満月になる。新暦では九月中頃過ぎにあたる。
(※注2)このような月の美しさを観賞するという美意識は、西欧などにはあまり見られない。元々中国の習俗であったが、日本の豊かな自然風土と四季移ろいの中で、日本独特の文化を作り上げた(日本という風土の中で、季節の移り変わりを感じ取り、それを楽しむ。日本人が持ちえた繊細で豊かな感性である)。
八月十五日の夜の月を観賞するのに、里芋の子の皮をつけたままで蒸した衣被を盛って供えたところから「芋名月」と呼ばれた。宇多天皇が寛平九年(八九七年)、宮中に観月の宴を催されたのが発端となり、月見に団子を供える習慣が出来、芒、芋等と共に三宝に十五個盛る。今日の月見だんごは、これに由来したものだ。
次第に武士や庶民へと広がり、月神や玉うさぎの絵像を掲げ、日が暮れかかると、月の出る方向に台を据える。そして、秋の七草を生け、酒・団子・里芋などをお供えし、女性は月に向って礼拝したのち、宴を開いた。又、旧暦九月十三日の夜を「後の月」といって枝豆や栗を供えた。仲秋の名月とは趣きも異なる日本特有の行事である。これを「豆名月」と呼ぶ。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月09日
◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(一)

◆秋の風情、仲秋の名月、月見と十五夜(一)
◆◇◆仲秋の名月(旧暦八月十五日)、月見と十五夜 、月の風情を愛でる
お月見はやっぱり秋、深く澄んだ天空にぽっかりと浮かぶ月・・・。空気が澄む秋は、月をさらに美しく深く鮮やかに見えるからであろうか。
詩歌の世界では、古来「月」といえば、秋の月を指す。これは、「花」といえば、春の桜を指すのと同じである。そして、「名月」といえば、陰暦八月十五日(新暦では九月中旬、今年は十月六日)夜の「中秋の満月」、「十五夜」をいう。できれば、先人にならって風雅に月を眺めてみたいものだ。
いにしえの日本人の月に寄せる想いは熱く、たくさんの美しい言葉を生み出した。十五夜への期待がふくらむ前夜は「待宵(まつよい)」、月は「小望月(こもちづき)」、待ちに待った当夜、雨や雲で見えないことを「雨月(うげつ)」「無月(むげつ)」。
そして十五夜の次の月が「十六夜(いざよい)」、十七夜の月を「立待月(たちまちづき)」、十八夜は「居待月(いまちづき)」、そして四日目の月を「臥待月(ふしまちづき)」と呼び、日毎に表情をかえる月の風情を愛でてきた。
また陰暦九月十三日の月を「十三夜」「名残りの月」と呼び、十五夜とならべて祭る習俗もあり、どちらか片方の月しかみない「片月見(かたつきみ)」は縁起が悪いという地域もある(十三夜を見ないことを忌む考え方は江戸時代後期にも見られた)。「栗名月」の名もある十三夜の風習は、中国にはない日本独自のものである。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月09日
◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(四)

◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(四)
◆◇◆節句とは、移り変わる日本の季節を楽しむ繊細な感性
古来より、日本人にとって節句とは、移り変わる日本の季節の節目、節目を感じ取り、心豊かに暮らせることを楽しみ祝う、昔ながらの記念日であった。春夏秋冬と季節が美しく移り行く日本では、気候の変り目の祝祭日のことを節日(せちび・せつび)といい、お供え物をしたり行事をおこなって祝ってきたという歴史がある。
この節日の供物、「節供(せちく)」という言葉が、節日そのものを指すようになって「節句」という言葉になったともいわれている。
◇五節句というように、現在にも五つの節句が伝えられてる。
1月7日、七草粥で新年を祝う「人日(じんじつ)の節句」
3月3日、雛祭りとして有名な「上巳(じょうみ・じょうし)の節句」
5月5日、男の子の成長を祝う、こどもの日「端午(たんご)の節句」
7月7日、織姫、彦星の物語で有名な「七夕(たなばた)の節句」
9月9日、菊花の香りの酒で月をめでる「重陽(ちょうよう)の節句」
それぞれの節句は、宗教行事として、地域の祭りとして、また子供たちの成長を祝う祝日として、様々な形で私たちの暮らしの中にいきづいていた。節句とは、日本という風土の中で、季節の移り変わりを感じ取り、それを楽しむ記念の日として、日本人が持ちえた繊細で豊かな感性だったのである。
これらは古来、宮中の行事であったり、中国から伝わった伝説であったりしたものである。それが長い歴史を経るうちに、地域の暮らしや風土にあったものへと姿を変えながら、現代の私たちに季節感を伝えてくれたり、暮らしのワンシーンを和やかなものにしてくれたりするのである。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月08日
◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(三)

◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(三)
◆◇◆重陽の節句(九月九日)、「栗の節句」「お九日(おくんち)」
菊と共に「重陽の節句」に関りの深いものに、その頃採れる栗があえう。中国にも重陽に栗を使った料理を食べる風習があるが、日本でも、重陽を一名「栗の節句」と呼んで、栗飯を食べる日としている地方がある(旧暦の九月九日というと新暦では十月にあたり、ちょうど田畑の収穫も行われる頃、農山村や庶民の間では、初穂を神仏に供えたり、栗ご飯を炊いて神仏にお供えして祝う)。
また、民間では「お九日」(おくんち)といって収穫祭の一環とする風習もあるようだ。「お九日」は九月九日を神の日、十九日を農民の日、二十九日を町民の日などと言って、神酒に菊の花を添えて、餅をつき(ヨギを入れたりする)、栗飯を炊いて神に感謝する稲の刈上げの祭りである。「お九日」に茄子を食べると中風にかからないとも言われている。
◆◇◆秋の農耕儀礼、八朔(はっさく・九月一日)、風鎮祭(ふうちんさい・九月上旬)
旧暦の八月朔日を八朔(はっさく)と呼んでいたが、新暦になって九月一日の行事になったが、「田面(たのも)節句」ともいう。「八朔たのもに出ん穂なし 九月九日に青田なし」といって、田を回って穂の出たことを賞めて、豊作を祈って「田のも団子」をつくり神仏に供えて感謝した。
農村では、八朔と二百十日は農家にとってはいちばんたいせつな時期であった。また、地域によっては、九月上旬、風鎮祭(ふうちんさい)が行われる。稲の穂が出る前あるいは出揃った時期が、二百十日や二百二十日の大風の季節と重なり、ことのほか農家の関心が強いことを意識した、農耕儀礼と考えられる。
◆◇◆豊かな自然風土と四季の移ろいの中で育まれた「年中行事」
太古より、私たちの祖先は、日本列島の豊かな自然風土と、季節ごとに変化する四季の移ろいの中で、恵み(恩恵)をもたらしてくれる自然に、大きな力の働きを感じ取っていた(プリミティヴな神観念)。そして、そこに住む我々の祖先の日本人は、農耕を生活の基盤に据えながら、さまざまな文化や伝統を育んできたのだ。
春夏秋冬の四季の変化の中で、豊作(豊穣)への祈りと感謝を捧げながら、毎年繰り返されるたくさんの民俗行事や伝統儀礼は、しだいに「年中行事」となりさまざまな習俗として今日に至りるのである。
こうした民俗行事や伝統儀礼の中には、日本の固有の行事もあるが、外来の行事が習合したものも数多くある。私たちの祖先は、こうした民俗行事や伝統儀礼を生活の一部として受け継ぎ守り伝えてきたのだ。
豊かな自然風土の中で育まれた祖先以来の文化(四季折々の年中行事・伝統儀礼)は、明治の改暦や時代の推移にもかかわらず、今日に至るまで連綿と生き続け、私たちの生活に活力と潤いを与えてくる。これからも、こうした民俗行事や伝統儀礼、祭りを大切にしていきたいものである。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月08日
◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(二)

◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(二)
◆◇◆「重陽の節句」(九月九日)、「菊の節句」「菊の節供」「菊の宴」
重陽の節句は別名「菊の宴」(平安時代には、観菊の宴が催され、詩歌など読み、菊の花を酒に浸した菊酒を酌み交わす)ともいい、古くから宮中に年中行事の一つとして伝わってきた。菊は翁草、齢草、千代見草とも別名を持っており、古代中国では、菊は仙境に咲いている花とされ、邪気を払い長生きする効能があると信じられていた。
その後、日本に渡り(菊は大和時代に中国から渡った)、古くより厄災祓いの日として、菊酒を飲んだり、菊の香と露とを綿に含ませ身をぬぐうこと(※菊の被綿・きせわた)で、長寿を保つともいわれ、不老長寿を願う行事として貴族のあいだで定着したようである。
これは、菊の持つたくましい生命力に少しでもあやかりたいというのが人々の願いだったのだ。※菊の被綿は、重陽の節句の前夜にまだつぼみの菊の花に綿をかぶせて菊の香りと夜露をしみこませたもので、宮中の女官たちが身体を撫でたりもしたといい、枕草子や紫式部日記の中でもその風習を窺うことができる。
紫式部(『源氏物語』)は、自らの歌集『紫式部集』にこんな歌を詠んでいる。「菊の花 若ゆばかりに 袖ふれて 花のあるじに 千代はゆづらむ」 また、清少納言の『枕草子』には、「九月九日は、暁方より雨すこし振りて、菊の露もこちたく、覆ひたる綿などもいたく濡れ、うつしの香ももてはやされて」という一節があり、平安朝の重陽の節会の様子を伝えてくれる。
さらに、『万葉集』には「百代草=菊」として登場し「父母が 殿の後方(しりへ)の 百代草(ももよぐさ) 百代いでませ わが来たるまで」(生玉部足国・いくたまべのたりくに)、『古今集』の頃から「菊」の文字として現れる「心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花」(凡河内躬恒・おおしこうちのみつね))。
また、花札で九月の役札には菊の花とともに「寿」と書かれた盃が描かれているが、これは菊酒の信仰を受けたものである。これら菊に対する信仰は、やはり中国の故事に由来している。周の時代、「菊慈童」(きくじどう)という名の男が、あるとき菊の露が落ちて谷川となっているところを見つけた。その水を汲んで飲むと、甘露のように甘く、心がさわやかになり、やがて仙人となって八百歳まで長生きしたという。
また、菊の花は皇室の紋章であり、日本を代表する花の一つだが、もとから日本にあったわけではない。奈良時代に、薬用として中国からやってきたのである。室町時代には、食用としてもさかんに栽培された。
菊の家紋は平安時代から宮中で使われはじめ、特に後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)が好んで使ったという(鎌倉時代に後鳥羽上皇が衣服や刀剣までこの文様を用いたことに始まると言われています)。
その後、江戸時代までは一般庶民でも菊紋を使っていたが(貴族にしろ武士にしろ、菊の文様を好んだのは、中国の菊慈童伝説「100年を経てなお童顔の仙人で在り続けた」等の故事にちなんで、延命長寿の霊力にあやかりたいと言う願いの現れであったようである)、明治二年に禁止され皇室だけの紋章に決まった(菊が皇室の紋章として制定されたのは明治二年で、意外に新しく天皇家は十六花弁の八重菊、皇族は十四花弁の裏菊と定められた)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月08日
◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(一)

◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(一)
◆◇◆「重陽の節句」(九月九日)、不老長寿を願う行事
陰暦の九月九日は陽(陰陽の陽)の数字の重なる日(中国の重日思想から発した祭日。重日とは月の数と日の数が同じ数字となる日付で、めでたい特別の日付と考えられた)であり、中でも九は陽数(奇数は縁起のよい陽の数とされてる)の最大値(九は一桁の奇数としては一番大きな数なので「陽の極まった数」として陽数を代表する数と考えられ)である九が重なることから、「重陽(ちょうよう)」の節句(「重九(ちょうく)の節供」とも呼ばれる)として五節句(人日、上巳、端午、七夕、重陽)の中でももっとも重んじられてきた。
中国ではこの日、茱萸(しゅゆ、和名:かわはじかみ)を袋に入れて丘や山に登ったり、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を願うという風習があった(中国には古くから山に登って天と地の神を祀るという思想があった。始皇帝や漢の武帝が行ったといわれる「封禅の儀」の祭祀と通じるものがある)。
これが日本に伝わり、平安時代には「重陽の節会(ちょうようのせちえ)」として宮中の行事となり、江戸時代には武家の祝日になる。その後明治時代までは庶民のあいだでもさまざまな行事が行われていたというが、残念ながら今では私たちの日常生活とは縁遠くなってしまった。
さかんに行われていた重陽の節句が、現代に引き継がれていないのは、旧暦から新暦にこよみが移り、まだ菊が盛んに咲く時期ではなくなってしまったことが大きな要因のようだ(「日付」に固定された祭日なので仕方ないが、元は晩秋の頃の行事であった。伝統行事は、もっと季節感を大切にしてもらいたいものである)。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月05日
◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(十)

◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(十)
※出羽弘明氏の『新羅神社考-「新羅神社」への旅』(三井寺のホームページで連載)を紹介する。出羽弘明氏は「新羅神社と新羅明神の謎」について、現地に出向き詳細に調べておられる。そこからは、古代、日本と新羅との深い関係が窺える。内容を要約抜粋し紹介する(新羅明神、白髭明神、比良明神、都怒我阿羅斯等、天日槍、伊奢沙別命、素盞嗚尊、白日神、新羅神など)。
◆◇◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎、丹後・山城-3
山陰地方に四道将軍の一人、丹波道主命が遣わされたことは、丹後地方が早くから大和朝廷と政治的に密接に結びついていたことが考えられる。大和朝廷の全国統一の過程で、丹後地方をはじめ山陰地方に重点が置かれたことは、逆にこの地方に大和朝廷に対抗するほどの勢力を持った豪族が政治、経済に強大な権力を持って存在していたことを意味し、丹後地方に雄大な前方後円墳が残された所以を示すものである(『弥栄町史』)。
溝谷神社に掲げてある『溝谷神社由緒記』には次のように記載されている。「当社は延喜式所載の古社にして、社説によれば、人皇第十代崇神天皇秋十月、将軍丹波道主命、当国へ派遣せられ、土形の里に国府を定め居住あり。或時、神夢の教あり、眞名井ノト(トはウラ又はキタとも云ふ)のヒツキ谷に山岐神(やまのかみ)あり、素盞嗚尊の孫、粟の御子を以って三寶荒神とし斎き奉らば、天下泰平ならんと。道主命、神教に従ひ丹波国眞名井ノトヒツキ山の麓の水口に粟の御子を以て三寶荒神と崇め奉る。其の御粟の御子は水口の下に新宮を建てて斎き奉る。因て、水の流るゝ所を溝谷庄と云ふ。溝谷村、字溝谷を旧名外(との)邑と云ひしは眞名井名ノトと云ふ字を外の字に誤りて云ひしものなりと。その後丹波道主命の子、大矢田ノ宿禰は、成務・仲哀・神功皇后の三朝に仕えて、神功皇后三韓征伐に従ひ、新羅に止まり、鎮守将軍となり、新羅より毎年八十艘の貢を献ず。其の後帰朝の時、風涛激浪山をなし航海の術無きに苦しみしに、素盞嗚尊の御神徳を仰ぎ奉り、吾今度無事帰朝せば、新羅大明神を奉崇せんと心中に祈願を結びければ、激浪忽ち変じて蒼々たる畳海となりて無恙帰朝しけれぱ、直ちに当社を改築せられ、新羅大明神と崇め奉る。因て今に至るも崇め奉して諸民の崇敬する所なり」
他にも弥栄町の隣町に当る中郡大宮町字周枳(すき)の大宮売(め)神社(周枳の宮―祭神天鈿女(あめのうずめの)命・豊受大神)ある。大宮売神社のある土地の周枳(すき)というのは、スキ国=新羅国の意であり、竹野郡の間人から竹野川沿の中郡大宮町にかけては、弥生時代には竹野川文化圏を形成しており、古代に渡来した人達の文化が栄えた地域であった。いわゆる出石族・出雲族が居住していた。
大宮売神社のある大宮町は竹野川に沿って古くから開拓された地域である。大宮売神社の祭神は天鈿女命・豊受大神であるが、これは五穀豊穣を願う祖神である。そして当地の式内社は全部豊受神(天女の一人が豊受の神)、大宮女は八神の一座、機織と酒造り(風土記には比治の真奈井、奈具社)の神であり、丹波道主命米の稲作は天女が降り、奈具の社にとどまったことから、稲作民族が定住したことを意味し、これが祖神となった。なお、豊受神は九州から来たという説もある。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月04日
◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(九)

◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(九)
※出羽弘明氏の『新羅神社考-「新羅神社」への旅』(三井寺のホームページで連載)を紹介する。出羽弘明氏は「新羅神社と新羅明神の謎」について、現地に出向き詳細に調べておられる。そこからは、古代、日本と新羅との深い関係が窺える。内容を要約抜粋し紹介する(新羅明神、白髭明神、比良明神、都怒我阿羅斯等、天日槍、伊奢沙別命、素盞嗚尊、白日神、新羅神など)。
◆◇◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎、丹後・山城-2
丹後半島は海人族が住んでいたと思われる。その海人族は九州の豊後(大分)国とつながりが深く、いくつかの共通性が見られる。和歌山県に古代の怡土(いと)国(福岡県)に因む地名が多いのと同様であるが、これは九州にあった国の氏族が、丹後や紀伊地方へ移住した痕跡ではないだろうか(あま、大野、やさか、竹野、矢田、はた等)。
丹後の「比治の真名井(ひじのまない)」は、豊後では国東半島の近くの速水郡日出(ひじ)町に「真那井(まない)」がある。また、丹後の伊根町の漁師の家と同じ構造の家が、豊後の南、海部(あまべ)郡に見られる。海部氏(海人族)が九州から中部地方に至る間に広く分布していたことの証拠であろう(海部郡は紀伊や尾張にもあり、阿曇(あずみ)の海人として朝鮮半島や江南の古代海人と関係が深い)。
丹後半島の中央部竹野郡弥栄町字溝谷に溝谷神社がある。溝谷神社の祭神は新羅(しらぎ)大明神(須佐之男命)、奈具大明神(豊宇気能売命、竹野郡弥栄町から溝谷を通り過ぎるあたりの船木には奈具神社(祭神豊宇賀能売命)がある)、天照皇大神の三神で、旧溝谷村三部落の氏神である。
当神社の創建年代については、当神社の火災により古文書が焼失し往古の由緒は不明であるが、延喜式(九二七年)記載の神社であることや、崇神天皇の時代の四道将軍の派遣と関係があること、新羅牛頭山の素盞嗚命を祀ったということ、四道将軍の子・大矢田ノ宿禰が新羅征伐の帰途、海が荒れて新羅大明神を奉じたこと、神功皇后が新羅よりの帰途、着船したこと、などから考えれば、当社は古代から存在し、かつ新羅系渡来人と深いつながりがあったことが判る。
スサノヲ(スサノオ)
2006年09月03日
◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(八)

◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎(八)
※出羽弘明氏の『新羅神社考-「新羅神社」への旅』(三井寺のホームページで連載)を紹介する。出羽弘明氏は「新羅神社と新羅明神の謎」について、現地に出向き詳細に調べておられる。そこからは、古代、日本と新羅との深い関係が窺える。内容を要約抜粋し紹介する(新羅明神、白髭明神、比良明神、都怒我阿羅斯等、天日槍、伊奢沙別命、素盞嗚尊、白日神、新羅神など)。
◆◇◆新羅神社考、新羅神社と新羅明神の謎、丹後・山城-1
京都府には北部から南部まで新羅関係するの神々が祀られている。北部では丹後地方、南部は山城地方の宇治市である。南部の京都盆地には「素盞嗚尊・牛頭天王」を祀る八坂神社や新羅系渡来人秦氏とつながりの深い松尾大社、賀茂神社がある。
丹後地方は日本海に面し、古来から大陸や半島との往来が頻繁にあった。またこの地方は弥生時代には王国があったといわれている。特に弥栄(やさか)町の新羅明神(溝谷神社)は渡来の人々(特に新羅系、或いは秦氏系の氏族)が祀ったといわれる。
さらに丹後地方に隣接する出石郡には、新羅の渡来人である天日槍(あめのひぼこ)と縁の深い土地である。また、京都府の太秦や園部町から続く丹波地方も新羅系渡来人の痕跡が非常に色濃く残る。
丹後地方の若狭湾に沿った地域は、新羅系渡来人である天日槍や都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)など伝承と共に、伊奨諾(いざなぎ)、伊奨冊(いざなみ)神話から始まり、山幸彦(天火明命(あめほあかり))の天降り伝承をもつ冠島や海人(あまべ)族の系図をもつ籠(かご)神社などがある。
丹後は元々は丹波国であったが、和銅六年(七一三)に分離し、丹波後国、丹後国となった。『和名抄』に、タニハノミチシノリ(田庭道後)とあり、南の大和からみて北側の奥にあるという意味であろう。
丹波は“たには”といわれ、豊受大神(穀物神)が初めてこの国に鎮座して神饌米を供したことから田庭と書かれたという。古代の「たには」国は、丹後、丹波、若狭、但馬を含む大国で、日本海を往来した海人族が大陸文明を取り入れた先進地域を形成していたようだ。
丹後半島には古代の伝承や説話が多く残っており、古代遺跡も多い残っている。特に天孫降臨と類を同じくする渡来人の漂着神話や伝承は多い。そして、数多く存在する神社は、弥生時代から古墳時代にかけての古代祭祀遺跡や古墳をその境内にもっているものも多い。
伝説で有名な神社には、秦の始皇帝の命で不老不死の薬を探しに来た徐福を祭る新井崎神社(与謝郡伊根町)、浦島と乙姫伝説(『日本書紀』雄略天皇二十二年)が伝わる宇良(浦島)神社(与謝郡伊根町)、更に、羽衣伝説で有名な乙女神社(中郡峰山町)や、矢田、波弥、名木、枳(からたち)の各神社(中郡峰山町)がある。
さらに、彦火火出見尊(山幸彦)を祭神とする元伊勢の籠(この)神社(雄略天皇が天照大神を伊勢に祀る前には当地に祀られていた)がある。この元伊勢といわれる籠神社の参道には天の橋立であるが、伝承によると、天にあった男神・伊奨諾大神が、地上の籠(この)宮の磐座(いわくら、太古の斎場)に祀られた女神・伊奨冊大神のもとへ通うため、天から大きな長い梯子(はしご)を地上に立てて通われたが、或る夜梯子が倒れてしまい天の橋立となったと伝えている。
大国主命が沼河姫と共に当地に住んだ時、姫が病に罹った時、少名彦命が治したという伝説に基づく小虫神社、大虫神社(与謝郡加悦(かや)町)。この加悦町は伽耶を意味し、朝鮮半島の人(高天原といわれる)の渡来してきた町であるという。
スサノヲ(スサノオ)